ドミノ・ピザが閉店ラッシュに至った理由

業界全体の動向と経済的背景
近年、日本の外食産業全体がコスト上昇や労働力不足の影響を受けており、特にフードデリバリー業界は競争が激化しています。
原材料費の高騰、最低賃金の引き上げ、そしてエネルギー価格の上昇が経営を圧迫し、多くの企業がコスト削減を迫られています。
加えて、消費者の購買行動の変化も大きな影響を与えています。
例えば、外食の機会が増加する一方で、手軽に食事を済ませたい消費者が増え、コンビニやスーパーの惣菜・冷凍食品市場が急成長しています。
この傾向により、フードデリバリーの利用が以前ほど必要とされなくなってきており、特に単価の高いピザ業界では売上減少が顕著になっています。
また、インフレの影響を受けて消費者の節約志向が強まり割引サービスやプロモーションの影響を受けやすくなっていることも業界の収益構造に大きな影響を与えています。
コロナ禍の影響と顧客の変化
新型コロナウイルスのパンデミックにより、一時的に宅配ピザの需要は急増し、多くの消費者が外出を控える中でデリバリーサービスの利用が拡大しました。
特に、ロックダウンや飲食店の営業時間制限の影響を受け、宅配ピザは手軽で安全な食事の選択肢として大きく成長しました。
しかし2023年以降、社会が正常化し外食需要が回復するにつれて、デリバリー需要は急速に減少しました。
加えて、リモートワークの縮小が進み、多くの人がオフィス勤務に戻ったことで自宅での食事機会が減少し宅配ピザの注文頻度が低下しました。
さらに消費者の節約志向が高まる中で、デリバリー費用の高さがネックとなりコストを抑えた食事選択へとシフトする動きが強まりました。
こうした環境変化により宅配ピザ業界全体が厳しい局面を迎えており、ドミノ・ピザもその影響を大きく受ける結果となっています。
ドミノピザの戦略とその限界
ドミノ・ピザは過去数年間、積極的に店舗数を拡大し、短時間配送エリアを広げる戦略を取ってきました。
特に競争優位性を確保するために、都市部だけでなく郊外にも新規出店を進め、短時間での配送網の拡充を図ることで、他のピザチェーンやデリバリーサービスとの差別化を試みました。
しかしこの拡大戦略にはリスクが伴っており、過剰出店による市場の飽和や、店舗ごとの収益バランスの悪化といった問題が顕在化しました。
採算が取れない店舗の増加により、全体の経営効率が低下し、一部店舗の閉鎖を余儀なくされました。
さらに、フードデリバリー市場の多様化が進み、Uber Eatsや出前館などのサービスが台頭したことで、従来のピザデリバリーという枠組みの中だけでは競争力を維持するのが難しくなりました。
加えて、消費者の嗜好が変化しより健康志向の食事や手軽に食べられる選択肢が求められる中で、ドミノ・ピザの従来のビジネスモデルが十分に適応できていない可能性があります。
このような複数の要因が重なり、拡大戦略の限界が露呈しつつあるのが現状です。
ドミノ・ピザの閉店店舗数の状況
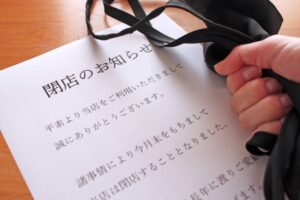
具体的な閉店店舗数の分析
2024年に入り、全国で172店舗の閉店が発表されました。
これは、全店舗数の約15%にあたる大規模な縮小です。この大規模な閉店は、ドミノ・ピザの経営戦略の転換点とも言えます。
特に都市部では競争が激化しており、既存の店舗が市場の変化に対応できなくなった結果、採算が合わなくなった店舗の整理が進められています。
加えて、地方の店舗では人手不足が深刻化し、十分なスタッフを確保できないことで、サービス品質の低下が避けられない状況になりました。
このような経済的・労働環境の変化が重なり、店舗数の調整が必要になったと考えられます。
さらに、デリバリー市場の多様化によっ、競争環境が変わり従来のビジネスモデルが通用しづらくなっていることも大きな要因の一つです。
都道府県別の閉店状況
特に都市部での閉店が目立ちます。
東京都、大阪府、愛知県といった大都市圏では、競争が激しく、採算が合わない店舗が閉鎖されています。
大都市圏では店舗数が多いため、同じエリア内での競争が激しくなり、収益性が低い店舗が淘汰されやすくなっています。
さらに、家賃や人件費の高騰が経営を圧迫し、特に収益性の低い店舗は閉店を余儀なくされました。
また、大都市ではデリバリーの選択肢が増え、
消費者が他のデリバリーサービスを選ぶ傾向が強まり、ドミノ・ピザの売上に影響を与えています。
一方、地方では別の要因が閉店の理由となっています。
地方では、労働力不足が深刻化しており、アルバイトや正社員の確保が難しくなっています。
その結果、十分な人員を確保できない店舗では、営業を継続することが困難になり、閉店が相次ぎました。
さらに、地方ではピザの需要自体が都市部ほど高くなくコスト面で持続可能な経営を行うのが難しいケースも多く見られます。
このように、都市部と地方のそれぞれ異なる要因が重なり全国的な閉店ラッシュにつながったと考えられます。
今後の閉店予測
今後も採算の合わない店舗の閉鎖は続く可能性が高いです。
特に売上が伸び悩むエリアではさらなる統廃合が進むと予想されます。
さらに、経済状況の変動や消費者行動の変化により、収益性の低い店舗が早期に見直される可能性が高まっています。
特に、地方都市では人口減少の影響も受けやすく、ピザの需要が思うように伸びない地域では統廃合がより積極的に進められるでしょう。
また都心部においても、家賃や人件費の高騰によるコスト増加が経営を圧迫しており、利益を確保できない店舗の閉鎖が避けられない状況です。
加えてオンライン注文の増加や競合の積極的な市場展開も影響し、既存店舗の維持がますます難しくなると考えられます。
宅配ピザ業界の競争激化

ピザハットとの比較と競争戦略
ピザハットは近年、セットメニューや期間限定商品に力を入れ、顧客獲得に成功しています。
特にファミリー層向けの大容量メニューや特定の季節に合わせたプロモーション戦略を積極的に展開し、売上を伸ばしてきました。
さらに、オンライン注文の利便性を向上させるために、アプリの改良やデジタルマーケティングへの投資を進めており、これが新規顧客の獲得に寄与しています。
一方、ドミノ・ピザも競争に対応する形で価格調整やプロモーションを行っていますが、消費者の選択肢が増えたことで競争は厳しさを増しています。
特に価格設定の変更による影響は顕著で値上げによって一部の消費者が離れ、より手頃な価格帯の選択肢へと流れている状況です。
また、デリバリー市場全体の変化に対応するためドミノ・ピザは新たなプロモーション施策を試みていますが、競争の激化により市場シェアの維持が課題となっています。
デリバリーサービスの多様化
Uber Eatsや出前館などのプラットフォームの台頭により、消費者はピザ以外の選択肢を容易に選べるようになりました。
これによりピザ業界だけでなく、飲食デリバリー全体の構造が変化しています。
特に寿司や丼もの、ラーメン、カレーなど、多様なジャンルの食事が宅配可能になり、従来ピザを選んでいた消費者の関心が分散しています。
加えて、健康志向の高まりとともに、サラダ専門店やヘルシーデリバリーの需要が伸びており、ピザのような高カロリーな食品が選ばれにくくなっている傾向も見られます。
その結果ピザ以外のデリバリー食品が人気を集め、ピザ業界全体のシェアが分散しています。
さらに最近では家庭用の冷凍食品の品質向上により、自宅で簡単にレストラン品質のピザを作れるようになったことも、宅配ピザの利用を減少させる一因となっています。
消費者の選択肢の増加
コンビニやスーパーの冷凍ピザの品質向上も、ドミノ・ピザにとって脅威となっています。
価格が安く手軽に購入できるため、特に一人暮らしや家族層に支持されています。
さらに、近年では冷凍ピザの種類も豊富になり、チーズや生地のクオリティも格段に向上しています。
多くのスーパーでは、本格的な窯焼き風ピザや、有名シェフ監修のプレミアム冷凍ピザなどが販売されるようになり、消費者にとってより魅力的な選択肢となっています。
加えて、電子レンジやオーブンで簡単に調理できる点も利便性が高く多忙な家庭や仕事終わりの食事としても重宝されています。
特に、近年の健康志向の高まりにより、低カロリーや高タンパク質のヘルシーピザなども登場し、冷凍ピザ市場の成長が加速しています。
こうした市場の拡大が、ドミノ・ピザの売上に影響を及ぼしていることは明らかです。
ドミノピザの価格戦略の変化
価格改定の影響と消費者心理
近年、ドミノ・ピザは値上げを行いましたが、コスト上昇を転嫁しきれず、価格競争力が低下しました。
原材料費や物流費、人件費の高騰が企業の経営を圧迫する中で、やむを得ず価格を引き上げたものの消費者の財布のひもは固くなっており、以前ほどの頻度で利用しなくなった顧客も増加しました。
特に、他のデリバリーサービスとの比較において、よりコストパフォーマンスの良い選択肢を求める消費者が増えており、割引キャンペーンの実施やセットメニューの強化といった施策も必要になっています。
さらに、インフレの影響で家計の節約志向が強まり、コンビニやスーパーの冷凍ピザへのシフトも進んでいます。
このような状況の中、価格競争力を維持するための新たな戦略が求められています。
コンビニやスーパーとの競争
前述のように、コンビニやスーパーのピザのクオリティ向上が影響を与えています。
特に、冷凍食品市場の成長は宅配ピザの売上に大きく影響を与えています。
近年、スーパーやコンビニでは種類豊富な冷凍ピザが登場し、消費者にとって魅力的な選択肢が増えています。
特に著名なシェフ監修の商品や本格的なナポリ風・シカゴ風ピザなどが手軽に購入できるようになり、家庭で手軽に楽しめることが強みとなっています。
加えて、近年の食品技術の進歩により冷凍ピザの品質が格段に向上し、焼きたてのような食感や風味を再現する技術が確立されました。
そのため宅配ピザよりも安価で手軽に楽しめる冷凍ピザを選ぶ消費者が増えており、特に一人暮らしや家族向けの需要が高まっています。
さらに、スーパーやコンビニでは特定の曜日や時間帯にセールを行うこともあり、割引価格で購入できる点も消費者の購買意欲を高めています。
これらの要因が相まって、宅配ピザ業界にとっては大きな脅威となっているのです。
デリバリー料金の見直し
燃料費や人件費の上昇により、デリバリー料金の見直しが行われました。
これにより、コスト負担を嫌う消費者が店舗受け取りや他の選択肢に流れる傾向が見られます。
特に都市部では交通渋滞の影響も加わり、配達時間の遅延が発生しやすくなり、デリバリーを利用する際の利便性が低下するケースも増えています。
この結果、一部の消費者は利便性を求め、フードコートやテイクアウト専門店などの選択肢を選ぶことが増えてきました。
また、スーパーやコンビニでも、簡単に調理できる惣菜や冷凍ピザのラインナップが充実し、デリバリー以外の選択肢がより魅力的になっています。
こうした流れの中で、ドミノ・ピザをはじめとする宅配業界は、配送料の適正化や付加価値の向上を図ることで、顧客の流出を防ぐ新たな施策を模索する必要に迫られています。
ドミノ・ピザの今後の展開
新しい戦略の提案
デジタルマーケティングの強化や、新たなメニューの開発を進めることが今後の鍵となります。
特に、オンライン広告の最適化やSNSを活用したプロモーションの強化が求められています。
さらに、個々の消費者の嗜好に合わせたパーソナライズドマーケティングの導入を進めることで、より効果的にターゲット層にリーチすることが可能になるでしょう。
また、割引やサブスクリプションサービスの導入も有効な手段となるでしょう。
特に、定期購入プランを設定することで継続的な利用を促進し、売上の安定化につなげることができます。
オーストラリア市場への影響
オーストラリアでは同社の業績が好調であり、今後の成長市場と見なされています。
日本市場の縮小を補うために、海外戦略をさらに強化する可能性があります。
具体的には、既存店舗のリニューアルや、新たな地域への進出を進めることで市場の拡大を図ることが期待されています。
さらに、オーストラリアの消費者の嗜好に合わせた商品開発を強化することも競争力の向上に寄与するでしょう。
国内店舗の強化施策
採算の取れる店舗への集中投資や、デリバリーの効率化を図ることで、収益性の向上を目指すと考えられます。
特に、配送ネットワークの最適化や注文から配達までの時間短縮を実現するためのシステム導入が求められています。
また店舗ごとの収益性を詳細に分析し、経営効率の向上を目指した戦略的なリストラを行うことが、長期的な成長の鍵となるでしょう。
閉店の経営的理由
従業員の雇用問題とその影響
労働力不足により、店舗運営が難しくなっているのも一因です。
特にアルバイトの確保が困難な地域では、閉店が加速しています。人材不足の背景には低賃金や労働環境の厳しさが挙げられます。
特にデリバリー需要の高まりに伴い、配達員の確保が重要になっていますが、競争が激しく他業種に人材が流出しているため、十分な人員を確保できず、結果として営業継続が困難になっています。
営業効率の低下とその対策
不採算店舗の閉鎖によって、より効率的な運営を目指していると考えられます。
特に売上が安定しない店舗では営業時間の短縮や人員配置の見直しなどの対策が講じられています。
また、デジタル技術を活用した業務効率化も進められており、自動注文システムやAIを活用した需要予測の導入が進んでいます。
さらに、デリバリー専用の店舗を設置することで従来の運営コストを削減し利益率を向上させる試みも進められています。
管理体制の課題
急速な店舗拡大による管理体制の不備も指摘されています。
経営の見直しが求められる状況です。
特にフランチャイズ店舗の管理体制に課題があり、運営指針の統一が難しくなっています。
そのため本部が積極的にサポートを強化し、経営の透明性を高める必要があります。
また、データ分析を活用し各店舗の業績をリアルタイムで把握することで、問題の早期発見と迅速な対策が可能になります。
こうした取り組みが、将来的な経営の安定化につながると考えられます。
コロナ禍の需要変化と影響
宅配需要の一時的な急増
コロナ禍で需要が急増したものの、現在はその反動で需要が減少しています。
特に2020年から2022年にかけては、多くの人が外出を控え、自宅で食事をとる機会が増えたことで、デリバリーサービスが急成長しました。
しかし、2023年以降は外食産業の回復や旅行・イベントの再開により、宅配の利用頻度が減少し、業界全体の売上にも影響を与えています。
加えて、景気の悪化による家計の引き締めもあり、消費者はより安価な選択肢を模索する傾向が強まっています。
人々の生活様式の変化
リモートワークの縮小や外食回帰により、宅配ピザの需要が減少しました。
パンデミック中は多くの企業が在宅勤務を導入していましたが、2023年以降はオフィス回帰の流れが進み通勤が再開されたことで、昼食や夕食を職場近くの飲食店で済ませる人が増えています。
また外出制限の緩和に伴い、友人や家族との外食の機会が増え、宅配ピザの利用回数が減少していると考えられます。
さらに健康志向の高まりや食生活の多様化により、ピザ以外の選択肢が増えたことも影響しています。
長期的な需要の見通し
今後も外食と宅配のバランスが変化する中で、新たな戦略が必要とされます。
デリバリー市場の成長が鈍化する中で、企業は顧客を引き留めるために、より魅力的なプロモーションや新商品の開発を強化する必要があります。
特に、サブスクリプションサービスの導入や、健康志向のメニューを取り入れた新しいピザの開発が求められています。
また、デリバリー以外の選択肢として、持ち帰り需要を拡大する施策も重要になるでしょう。
こうした取り組みが、長期的な成長のカギを握ると考えられます。
多店舗展開の戦略とリスク
ドミノピザの拡大戦略
急拡大した結果、収益性の低い店舗が増加し、閉店ラッシュにつながりました。
特に、都市部では短期間で複数の新規店舗を開設したものの、既存店舗との競争が発生し、
売上の分散が生じました。
また、郊外や地方都市への進出も進めましたが予想よりも市場規模が小さく採算が合わないケースが多発しました。
このような背景から、無理な店舗展開が経営に大きな負担をかける結果となりました。
新規出店の地域分析
今後はより慎重な出店戦略が求められます。
特に、事前の市場調査を徹底し、地域ごとの消費動向や競合状況をより詳細に分析する必要があります。
加えて、新規出店に際しては短期間での採算性の確保を重視し、実験的な小型店舗の展開やデリバリー専門店舗の導入など、リスクの少ない戦略を採用することが求められます。
さらに地方都市では需要が安定しているエリアに集中するなど、経営効率を考慮した出店が重要になります。
リスク管理の不備
急成長に伴い、適切なリスク管理が行われなかったことが課題となっています。
特に、拡大期には多くのリソースが新規店舗に投入されたため、既存店舗の管理が疎かになり、売上低下やスタッフ不足が深刻化しました。
さらに、急速な展開により立地選定の精度が低下し、顧客の動向を十分に考慮しないまま出店するケースも見られました。
今後はより持続可能な成長を目指し、経営の安定化を図るための包括的なリスク管理が求められます。
ニュースとメディアの影響
報道によるブランドイメージへの影響
閉店のニュースが広がることで、ブランドイメージの低下につながる可能性があります。
特に、消費者の間では「経営不振」や「サービスの質の低下」といったネガティブな印象を持たれることが多く、これが売上や新規顧客の獲得に影響を与える可能性があります。
さらに、SNSや口コミサイトでは情報が瞬時に拡散されるため企業側の対応が後手に回ると、
より深刻なブランドダメージを招く危険性があります。
PR戦略の見直し
消費者の信頼回復のために、新たなPR戦略が必要です。
具体的には閉店の理由や今後の展望を正確に伝え、ブランドの信頼性を高める努力が求められます。
例えば、経営改善の取り組みや新たなサービスの導入、品質向上への施策を積極的に発信することで、ポジティブな話題を作り出し、ブランドイメージの回復を図ることができます。
また、消費者と直接コミュニケーションをとる機会を増やし、信頼関係を構築することも重要です。
消費者への情報発信の重要性
透明性のある情報提供が、ブランドの信頼回復に寄与するでしょう。
特に、公式ウェブサイトやSNSを活用して、閉店に関する情報を明確に説明し消費者の不安を軽減することが求められます。
また定期的に企業の経営状況や新しい取り組みを発信することで消費者との関係を強化し、
ブランドの信頼性を高めることができます。

